2.学習院への赴任で高まった創薬への関心、そして起業へ
――柳先生の中で、応用研究への関心が高まったのはいつ頃からでしょうか。学習院に来られてから変化があったのでしょうか。
柳 まさにそのタイミングでしたね。これまで基礎研究一辺倒でしたが、研究者人生も後半に差し掛かると、研究成果を社会に還元したい・形として見えるものにしたいという思いが強くなってきました。昔から「応用できるものがあれば挑戦したい」という気持ちはありましたが、年齢とともにその比重が増してきた感じですね。
面白いのは、創薬に取り組む中で新しい生理的メカニズムが見えてくることです。たとえば「なぜ、マイトルビンでミトコンドリアが活性化するのか?」という疑問から、ミトコンドリアを増やすスイッチの存在が示唆されるなど、応用から基礎へのフィードバックもあります。
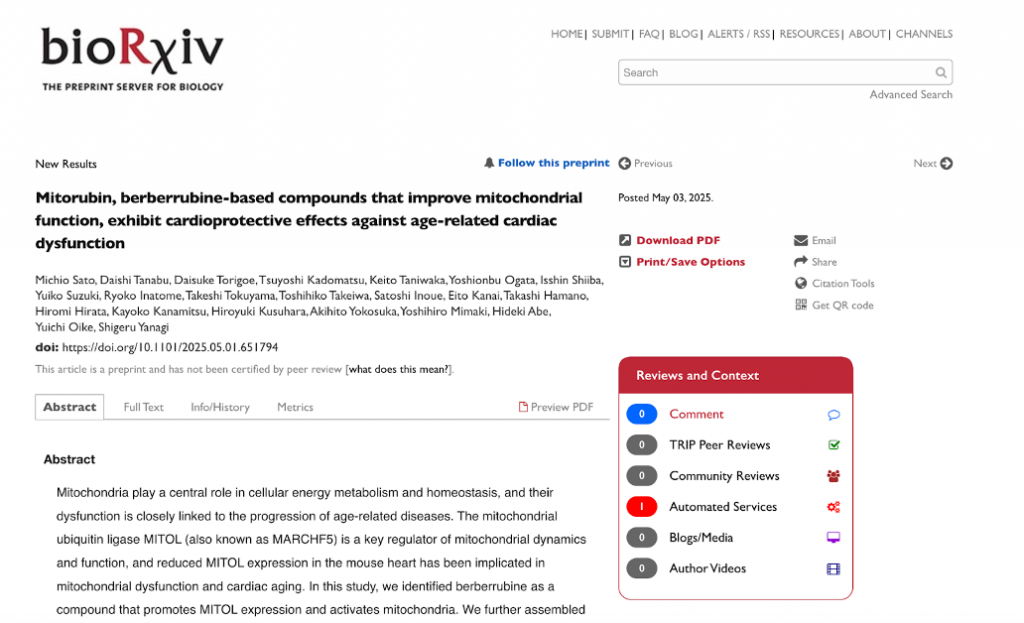
先ほど、「メカニズムは後から解明すればいい場合もある」と言いましたが、その“後から”は単なる後追い説明にとどまらず、基礎科学の地図を書き換える可能性もあるということです。そのことは、学習院で応用研究に力を入れて初めて実感した点です。
―谷若社長がマウスでの評価を行ったのも、学習院に来られてからですよね。そのきっかけは?
谷若 培養細胞の実験で得られた作用が生体(マウス)でも同様に現れるかを確かめる必要がありました。細胞とマウスでは反応がしばしば異なるので、まずは条件を絞ったマウスでの短期評価から着手し、そこをクリアして初めて応用研究に進めると考えました。
柳 そうは言っても、マウスに与えるのもそんなに簡単じゃないんですよね。ゾンデと呼ばれる細い管を使って強制的に経口投与する方法もありますが、餌に混ぜて食べさせようとすると、味が美味しくなかったり警戒されたりして食べてくれないときがあります。
そういうとき、谷若くんはマウスが興味をもつように寒天に混ぜたゼリー状の餌をつくるなど工夫していました。こうした現場での工夫は起業後も一貫していて、彼の発想力と行動力は応用研究や事業化にまさにフィットしていると実感しています。
―谷若社長は、小さい頃からそういう発想や工夫をされることが多かったのですか?
谷若 正直、意識したことはありませんが……あまり深く考えずに、思いついたらすぐに行動してしまうタイプというのは、その通りかもしれません(笑)。
NEXT> 3.創業当時の資金難と、理学部同窓会との出会い
