【お申込みはこのページの「お問い合せ -CONTACT US」から!】
平成29年の総会・講演会・懇親茶話会は、6月25日(日)に学習院女子大学@戸山キャンパスをお借りして開催されます。
今回の講演会は、中山慎太郎先生(平14仏)の「愛を歌う詩人たち―フランス詩をめぐって―」。リヨン第二大学で博士号を取得し、この3月までフランス語圏文化学科(旧フランス文学科)の助教を務めていた気鋭の若手研究者のお話をぜひ聞きにいらしてください!

【お申込みはこのページの「お問い合せ -CONTACT US」から!】
平成29年の総会・講演会・懇親茶話会は、6月25日(日)に学習院女子大学@戸山キャンパスをお借りして開催されます。
今回の講演会は、中山慎太郎先生(平14仏)の「愛を歌う詩人たち―フランス詩をめぐって―」。リヨン第二大学で博士号を取得し、この3月までフランス語圏文化学科(旧フランス文学科)の助教を務めていた気鋭の若手研究者のお話をぜひ聞きにいらしてください!

下記の通り、今年も「桜友会文学部同窓会 総会・講演会・懇親茶話会」が開催されます。皆様ふるってご参加ください。


日時/平成28年6月19日(日)午後1時30分~午後4時30分(開場午後1時00分)
会場/学習院創立百周年記念会館
[総会・講演会] 午後1時30分~午後3時20分 正堂
[講師] 加藤耕義先生(学習院大学外国語教育研究センター教授)
[演題] 学習院で遊んだこと、学んだこと —— 音楽の楽しみ、グリム童話の魅力 ——(ミニコンサート付き)
[略歴] 1963年東京生まれ。学習院中等科・高等科、学習院大学文学部ドイツ文学科卒業。1989年から1991年までドイツ・フライブルク大学留学。1994年、学習院大学人文科学研究科博士後期課程単位取得退学。現在学習院大学外国語教育研究センター教授。公益財団法人ドイツ語学文学振興会理事。練馬区演奏家協会運営委員。専門はグリム童話およびドイツ語圏の昔話研究。
[ミニコンサート] 加藤耕義先生(オーボエ)、笹沼樹さん(チェロ)
[略歴] 笹沼樹(ささぬまたつき)さん。1994年東京生まれ。7歳でチェロと出会い、9歳で本格的に始める。2011年、第65回全日本学生音楽コンクールチェロ部門高校の部第1位及び日本放送協会賞受賞。2013年、ザルツブルク=モーツァルト国際室内楽コンクール2013第1位。現在、「チェロアンサンブル・サイトウ」奨学金を受け、桐朋学園大学ソリストディプロマコース、並びに学習院大学文学部ドイツ語圏文化学科4年在学中。
[懇親茶話会] 午後3時30分から午後4時30分 小講堂
[参加費] 3000円
申込手順/
[ゆうちょ銀行からの送金先]
ゆうちょ銀行 00160-4-773892 桜友会文学部同窓会
[その他の金融機関からの振込先]
ゆうちょ銀行〇一九(ゼロイチキユウ店)当座0773892 桜友会文学部同窓会
お申込み・お問合せ先/桜友会事務局 FAX 03-3988-3853 TEL 03-3988-3288
文学部同窓会のFacebookページを作りました。ぜひ「いいね!」をお願いします。
→学習院桜友会 文学部同窓会
LINEでも文学部同窓会の情報を発信しています。こちらのQRコードから友だち追加をお願いします。
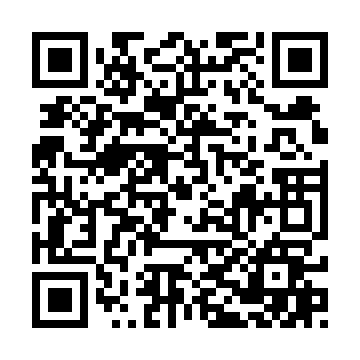
平成26年6月22日(日)、学習院女子大学(戸山キャンパス)において、文学部同窓会の平成26年総会・講演会・懇親茶話会を開催いたしました。
例年は目白キャンパスの創立百周年記念会館を使用しておりますが、本年は同会館が改装中のため、学習院女子大学の教室と食堂をお借りすることになりました。
【桜友会文学部同窓会協賛】 学習院女子大学 岩崎先生ゼミ特別授業(公開)について
戸山キャンパスの学習院女子大学において、以下のとおり公開授業が開催されます。
予約等は不要です。沢山の方々のご来場をお待ちしております。
来たる11月26日(土)の14:00から、学習院創立百周年記念会館1階正堂において「第66回学習院大学史料館講座」が開催されます。
今回は「日本美術史のはじまり―ウィリアム・アンダーソンと大英博物館―」 と題して、立命館大学でポストドクトラルフェローを務めておられる彬子女王殿下がご講演されます。文学部卒業生の皆様、ぜひ連れ立って参加いたしましょう。なお入場料無料・予約不要とのことです。
詳細は史料館のHPをご覧ください↓
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/ua/new.html#wa
※ポストドクトラルフェロー・・・博士研究員のこと。
去る平成22年6月27(日)、学習院創立百周年記念会館小講堂において、平成22年度桜友会文学部同窓会総会が開催されました。今回は、ご病気で療養中の篠沢秀夫会長も出席されました。会場には、ALS(筋委縮性側策硬化症)と闘う篠沢先生を取材するNHKと文藝春秋社のスタッフの姿も見られました。