去る7月7日、学習院創立百周年記念会館にて、法学部同窓会総会が開かれました。 講師に岩田 公雄 氏(昭49卒 )をお迎えしての講演会、引き続き行われた懇親会と、多数の参加者のもと盛大にとり行われました。
平成24年度法学部同窓会総会・講演会
講師 岩田 公雄 氏(読売テレビ放送報道局特別解説委員 昭49法卒)
演題「世界の報道の最前線に立って」
「講演詳細」
世界の報道の最前線にたって
みなさん今日は岩田でございます。どうぞ宜しくお願い致します。昭和49年法学部法学科卒業でマスコミに入って38年目になります。自分は事件記者から入って後に海外の初代マニラ支局長を3年間経験し天安門事件等を経験しました。
まず、なぜこの道に入ったかというと、学生時代すでに、東大紛争とか新宿騒乱とかの場面もあり学習院も同じような状況がありました。そんな学生時代に“なんでこんなことになるのか?”といつも現場に行っていました。ヤジ馬でもない、ノンポリでもない複雑な立場に立っていました。世の中の動きが騒然とする中で、3年のころから“自分は歴史の接点に身を置いて人生を終わりたい。”と痛切に思いました。テレビの記者として入ってみて、出来れば世界の現場に立ってみて伝えることが大事なんだろうと思って、これしかないとマスコミに決めました。“読売テレビ”の最終面接で“なぜマスコミを目指したいのか?”の質問に対し、“自分の人生を歩むのなら、出来れば出来事の接点、歴史の接点に身を置いて人生を進めたい。それで自分の一生をおくれたら本望だ。入らせていただきたい。”と言ったのを覚えています。おかげさまでなんとかもぐりこむことができ、事件記者から始まって現場を見ることになりました。大阪府警のキャップ等を経験し、その後に、フィリピンのマニラ駐在員になります。
最初はマフィアルートの武器密輸事件の取材に行きました。そのような事件の時に、必ず皆が言うのは、“その取材は岩田だ”と。なぜなら、“体が大きくて喧嘩しても勝つかもしれないし、使いべりしない。”ずっと今まで言われ続けて38年なんですね。誰もいまだに知能のことを一つも言ってくれないのが非常に不満であります。取材に行っているときに大変な事件に遭遇します。あの三井物産若王子支店長誘拐事件です。3日間徹夜をして取材しました。
そして、妻を帯同して3年間マニラに行きました。その在任中の最後の部分に1989年6月3日から4日の天安門事件の最終局面、あの血の惨劇事件の現場に立っておりました。戦車100両と機関銃の実弾が飛び交っている中にたっていて、“ああたぶん命を失う瞬間がここできたのだろうな。まあしかしこの道を選んだのだから、歴史の接点に触れたいと。”まさかこんな局面で民主化闘争があんな形の悲劇になるとは。全く想定していないことが現場で起きているわけです。地を吹き出して倒れている人が、リヤカーとか担架で運ばれてたり、撃たれて死んでいる人がたくさんいる現場を見て、“国家とは何か?民主主義とは何か?”を思い、改めて強い憤りを感じて、今でもその部分はトラウマとして残っていますし、現在でも中国を見る視線はそれが外れていないわけです。実はこの取材のなかで日本の記者は、“危ないから中国国外へ出ろ。避難しろ。”と言われている中で、ちょっと命令を無視して最後まで踏みとどまった一人なのですが、CNNの記者から、“なんで日本の記者は居なくなるんだ。”と言われたときに、“日本から命の危険があるから帰れ。”と言われていると答えたときに一言言われたのが、“本当に自分で現場に触れてみて、臭いも嗅いでみないで、何を遠隔から、東京の地から、今こんなことが起きています。ということが伝えられるのだろうか?それは現場にいるから伝えられるのだろう。それは危険だと私も思うよ。でもジャーナリストの道を選んだのだから、当然そうしなければいけないのだろう。乗り越えなければいけないんだ。”と言われたときに私は、“あなたの言う通りだ。もしあなたと将来奇跡的に会うことができたら、私がここを生き延びることができたら、私も現場に踏みとどまっていろんなことを見てきたよ。と伝えたいね。今あなたにはそれしか言えない。”と言ったら、最後手を出して、“そうか。Good Luck!将来どっかで会えたらお互いに頑張ろう”と言われて別れました。その言葉がずっと残っていて、帰ってきてからもマネジメントの世界に行かないで“生涯一記者で終わりたい。”と完全に思いました。
実は、1989年天安門事件の現場で青年4人と肩を組んだ写真があります。2年前でしたか中国人として初めて人権活動家の劉暁波さんがノーベル平和賞をもらいました。ところが、本人は投獄中、奥さんは軟禁中で、結局授賞式に誰も出ることができなかった。という初めてのケースがあったわけですが、天安門事件の当時、惨劇の3日くらい前の時に、学生のリーダーと写真を撮ったのがありました。赤い鉢巻をして汚いTシャツを着た青年4人と肩組んで撮っている写真があり、その中の一人が劉暁波さんでした。あれから23年たっています。経済大国になったのは認めざるを得ませんが、人権とか民主主義とかは、いまだに否定的というか、本当に信頼される大国になるなら、そこも、つきつめてやってほしいと番組でも言っています。
また、北朝鮮は、よくもエネルギーがあったと思いますが、キムイルソン主席が80歳の時に3日間生中継を実現しました。全部自分で企画して交渉して1年かかりました。
あと内戦で虐殺のあったルワンダですが、私が行った時にはホテルは全て破壊されており、命がけの取材でした。全くの無政府状態の国で取材をしました。いまは、一転して優等生みたいな国になっています。こうなったのは教育なのです。もう一回国家建設をはかり、民族対立を乗り越えた。という形になっています。私の見た内戦の現実はあまりにも悲劇的すぎて、記者でなかったらこんな悲劇をみることがなかったのにな。と思って佇んでいました。
今まで記者で良かったな。と思うことは、憧れのアウンサンスーチーさんに自宅軟禁中でしたが、ノーベル平和賞をもらった直後に会うことができました。スーチーさんはキングスインギリッシュですが、私はマニラ英語で単独インタビューに臨みました。パッと出てきた美しさに唖然として英語が出てきませんでした。まさしく“凛としてたおやか”でした。軟禁から解放されたのは、やっと今年です。軍事政権のカモフラージュかどうかはもう少し見なければいけませんが、ただ、ミャンマーは動き始めていますから元に戻らないと思います。非常に優秀な英語のできる民族です。工場を作るにしても何にしても有望な場所なので、世界がどんどん進出していく中で、日本がちょっと遅れているのではないかと言われています。ですから、ミャンjマーが変わってくれれば有難いと思ってみています。
日本が今後の成長戦略含め極めて大事な時に来ているときに、“政治がこういう状況で果たしていいのか?日本が将来アジアの孤児にならないようにするためにどうしたらいいか?”みなさん考えなければいけない時だと思うのです。日本のこれからの若い人の教育の問題とか、もう一度作り上げなければならないと思います。かつての明治維新の日本。終戦後の日本みたいに、エネルギーを統一して日本の再生を図ろうとしている中で、技術とかが外国に負けているわけではありません。これからはやはり海外です。今日も竹中さんと一緒でしたけど、“岩田さんね。ダボス会議のアジア版をやったとして、韓国人が運営したら、全ての分科会を英語で行っても誰も困らない。”と言われました。日本ではそうはいきません。やっぱり教育の問題は大事です。これからの学生にどういう環境を作ってあげて、学習院という素晴らしい環境の中で、かつ学生一人一人に意思を持たせるような教育をしていかなければダメだと思います。学習院は、環境が良くてのんびりして、確かにいい生徒さんばかりだと思いますけれども、もう一度先輩方が強い意思をもって生きてきたように、一人でも自立して飛び込んでいくような生徒をどんどん輩出して、世の中に出て行って、日本の再生とか、輝ける時代を築く学習院の後輩が出てくるのを期待するとともに、その一助となるなら、またいろいろなことをやらせていただければと思っています。最近は桜友会のバッジをつけてほとんど番組に出ています。今はプロデューサーもあきらめて、“また学習院のバッジをつけているよ。”と言われていますが、これからも胸にはバッジをつけて活動していきます。学習院のさらなる発展の一翼になれればと思っております。まだまだ現役として、本当に、生涯一記者と思っていますので、会社からとか世の中から、“もういいよ”と言われないように、張り切ってもうしばらくはやらせていただきますので、是非またご指導ご鞭撻宜しくお願い致します。
ご清聴有難うございました。
去る7月16日、学習院創立百周年記念会館にて、法学部同窓会総会が開かれました。
講師に佐々木 毅 氏(学習院大学法学部教授)をお迎えしての講演会、引き続き行われた懇親会と、多数の参加者のもと盛大にとり行われました。
平成23年度法学部同窓会総会・講演会
講師 佐々木毅氏(学習院大学法学部教授)
演題「西洋政治思想のユニークさについて」(要旨・抜粋)
西洋政治思想史は、古代ギリシャ・ローマから始まります。その頃に、アジアと西洋の違いが意識化されてきまして、西洋の研究者たちが、西洋とは違うものとしてのアジアが、対の概念として頭にあります。彼らからすれば自分たちと非常に異質なものであるという考え方ですね。で、これが実はこの西洋政治思想史というものの骨格部分をなしているひとつの特徴であります。
アジアの中身はもう適当に変わるんですね。いろいろ変わる。だけど、自分たちはそれとは違うものだという意識があります。違いがいわば視覚化されたのが紀元前5世紀頃と言われております。ペルシャ戦争があり、ダレイオス一世やクセルクセス大王が、100万とか200万の大軍を率いてギリシャ世界に攻め入ってきました。有名なマラトンの戦い、テルモピュライの戦い、サラミスの海戦などがその中で繰り広げられるわけですが、そこでお互いが、異質性、違ったところを自覚する、認識するというところが、話の始まりです。そこで私は政治共同体という言葉を使って、ギリシャ人たち、あるいはやがてローマ人たちが作った政治のイメージというものをお話しします。
ペルシャ人から見るとギリシャ人は変な人たちだと。どうして変かと言いますと、100万も200万も大軍を率いて攻め込んでいるのにさっぱり見えない。100万に対して50万が戦うならともかく、1000とか2000とかでも立ち向かってくるというのは、極めて理解しがたい、不可解な人たちであると。しかもペルシャは大王の下、統率が効いているという体制、ところがギリシャ人たちは自分たちは自由だと言って、大王らしきものも存在しない。そして、死ぬまで戦う。敵に背を向けないで、死ぬまで戦うということを、当然のごとく考えている。他の地域であれば大きな数の軍勢を率いていればみんな逃げて行くのに、どうもここはなんか変だと。どうしてそうなのか、というのが、アジア型であるペルシャの側から見たクエスチョンなわけです。
ギリシャの歴史家ヘロドトスが、このへんのことをいろいろと対話を交えて書いた「歴史」という作品を残しておりますが、そこで、ペルシャの王宮にいるスパルタからの亡命者と大王との対話を記しております。亡命してきた人間は「本当のことを言っていいか?」「ご機嫌を損ねることを言っていいか?」と断ってからいろいろ話を始めた。何よりもこのポリス・・・ポリスとはいわゆる都市国家ですね。都市国家あるいはそこの基本的な共通のルールであるノモス、これは法と訳すとちょっと狭すぎるのですが、法や諸制度あるいは生活態度を含めた意味でのノモスというものを自分たちの支配者と考え、これに対して絶対服従であるということが彼らの基本的な生き方である。従って、大王がいようがいまいが、大王がいるから頑張るというのとは関係なくいわば一種の抽象的な概念、理念と言ったようなものにコミットメントしているということが、非常に大きな違いである。これに対して大王は「なんかよく分からない」と言うわけであります。
再度攻め込んでいき、これも有名なテルモピュライという非常にこの狭いところでの戦いになるのですが、スパルタ王のレオニダスが、三百人のスパルタ兵を引き連れて陣取るわけですね。そこをまた、あの何十万人が攻め込んでいく。ペルシャとしては数を見せさえすれば相手は逃げるんじゃないかという作戦ですが、なかなか逃げない。髪を剃ったり、体操をやったりしているということで、やる気があるのかないのか、まあこんなようなことが縷々書かれているわけです。300人プラスアルファと何十万人ですから、いずれ決着がつき、もちろんスパルタ王と300人はここで死ぬわけであります。戦争を通した出会いが大変面白く書いてあるのですけれども、そこでギリシャ人の作った仕組みというものがクローズアップされるわけであります。これは歴史的に変化していくのですけれども、基本的には一定数の平等な人々からなる共同体でありまして、もちろんギリシャですから奴隷もいるわけで、これは全然別でして、自由な人々、あるいは相互に平等な関係にある人々が中心になって政治共同体を作る。そしてその政治共同体の存続と栄光というものが一番のプライオリティ、優先度の高い目標であると。もちろん、各メンバーは物凄いエネルギーをそこでの政治や軍事活動に注ぎ込むわけで、ポリス、ローマ、栄光、あるいはそのポリスにはそれぞれ神がおりますから神の栄光もちゃんと立てる。個人レベルで言えば、やはり名誉というものが最高であると。他人に、優れた能力を政治、軍事その他、公共の場で示すということ、そして、それが後世にまで伝えられることが非常に大事ですね。死んじゃったら終わりっていうんじゃ、あまり頑張る気力もないわけですよ。だからそうやって、他のポリスというものが存続する限り、歴史が書かれる。記憶が伝えられる、あるいは思い出される。そうするとある種の、永続性、自分の生命の持っている永続性というもの、少なくとも自分の生命が消えると同時に全てが終わってしまうということとは違う可能性が開けてくる。公共の場で目覚ましい働きをすることが、そのための条件です。それなしに、自分が後世に残るということは絶対にあり得ないということであります。
アジアはどう見えるかというと、1人の権力者が他の人々の自由を奪って、極端なことを言えば、ムチで脅しながら、統治をしている体制に近いというようなイメージでとらえられているように見受けられます。ですからアジアは、誰か中心的な人物がいる限りは持っているけれども、この人がいなくなると皆、蜘蛛の子を散らすように逃げてしまう。共同体を作るという感じとは非常に違う。むしろ、権力者を中心に、さまざまな利害を持って支配という関係のネットワークができているというように、ギリシャ人たちはイメージしたわけです。有名なヘーゲルは「古代においては若干の人間が自由であった」と。で、「近代においては全員が自由であった」ということをいいます。で、「アジアにおいては1人だけが自由であった」、ですね。その権力者だけが自由で、あとはみんな・・・奴隷とは言いませんけれども隷属していたんだ、こういう言い方をします。
若干の人々が自由であった。だから奴隷もいるし、それに女性は少なくとも家の中にずっととどまっているという感じでなるわけですから、決して、今のような仕組みとは同じではありませんが、しかし若干の人間が自由であってお互いに平等であるということは、政治的に見ますと大きなことであると私は思っております。で、このような政治共同体というのは、キツいといいましょうか、名誉を求めてお互いが争い合うという内部構造を含んでいる。他人よりもより多く共同体に貢献したいという気持ちを、いかにしてお互いが競争しながら、高めていくか。競争の場としての政治というのが非常に強い性格を持っておりますから、俗に言うと今度は権力争いが、そこでは日常的であると。
ギリシャ世界の中にソクラテスという変なおじさんが出てきまして、変なおじさんというのは風体が変であること、また、生活態度が変であるということ、広場でふらふらしながらはだしで歩き回ってですね、人々の知的能力を試して、いかにあなたは無知であるかということを分からさせてあげようということをやってるわけであります。結局、名誉を求めて政治共同体の中で泳いでいくというのが人間の姿という、まあそこに尽きるということに満足できるのかと、それが本当の人間のあり方なのかというようなことを、問うようになってきます。そこで彼は、魂という概念を持ち出す。肉体とは違う独立した固有の価値のあるものとして魂を持ち込んできたんですね。そして、実はこれが人間にとって大事なものであって、それに比べると健康とか財産とか名誉なんていうものは、大したものじゃないということを言い始めるわけです。一種の倫理革命でありまして、政治活動で名前を上げて政治共同体のために貢献することに尽きるというような考え方に対して、そうじゃないと。つまり、それぞれ人間が持ってる魂というものをいかに優れた状態に保つか、いい状態に保つか、あるいは魂を傷つけないようにするか、あるいは、神とつながりうる魂というものをいかに育てていくのか、あるいは磨いて行くのかといったようなことに、彼は関心を向けさせようとしたわけです。
この魂への関心というものは政治的観点から見れば、政治から脱出して内面世界、究極の価値を求めようとする傾向を非常にはっきりと示しているわけです。内面へ内面へと向かうと、自分たちが帰属すべき世界が何なのかということが改めて問題となります。非常に特徴的な言葉にコスモポリスという言葉があります。ポリスですから国家です。コスモだから宇宙の国家ですね。これのメンバーになるのが人間の理想ではないかといったような議論が出てまいります。要するに自分のアイデンティティというものを、目に見える世界から剥がして、いわばこのコスモポリスという観念的共同体といったようなものに求めるという考え方ですね。それが行きつく果てにキリスト教世界というものがやがて登場してきます。
キリスト教世界では神という概念がある。コスモポリスというのは神の国ということですね。神の国のメンバーになるかどうか。なれるかどうか。誰がそれを可能にしてくれるのか。あるいは誰がそれを判断するのかというあたりが、政治思想史的にも大変面白いテーマなんですが、私がここで信仰共同体という言葉を使うのは、もうちょっと深刻な意味においてであります。信仰共同体とは何か。信仰を同じくする人間たちだけが、共同体を作れるという考え方であります。一緒に共存していく条件として信仰のウエイトが非常に高くなっているということです。キリスト教と申しましても当時はカトリック教会ですから、普遍的一体的キリスト教世界というものを目指していたわけで、それに入らないグループは異端として十字軍その他を派遣する。その意味で同じ信仰を持っている人々とそれが作る共同体のメンバーになるということが、人間が一緒に生活していく上での非常に決定的な条件であるとなれば、当然のことながら、その信仰の一体性を現実的に保障し確保していく人がいないとならない。観念的共同体ではもはやなくて、目に見えるなかで信仰の共同体というものを作って行くとなると、当然その信仰の管理運営機関が必要であり、責任者が必要になってくるということになります。教会という組織、そして、それを代表するローマ教皇が、この信仰共同体の管理運営責任者になっていき、それに比べて王様とか領主とかが、信仰共同体のメンバーにふさわしくない行為をすれば破門されるということになる。ということは、王様その他に対するいろいろな義務はもはや無効になる・・・ここが非常に大事なわけです。例えば王様がいろいろ約束しても、破門になってしまうと、もはやその約束を守る必要がないということで、経済活動もこの信仰範囲内で基本的に営まれる、それを超えては契約も有効性を保障するものは何も存在しないというような議論も出てくるわけです。そして、信仰共同体のメンバーにふさわしくないと判断されますと、王様であればその地位を奪われるということが起こる。この信仰共同体、つまり信仰を共有する者たちの間においてのみ共同可能である、一緒に生活することが可能であるという議論は非常にユニークであると同時に、これまた大変重い概念です。ですから、宗教改革が何を意味したかといえば、まさに、信仰共同体が割れたということなんですね。そうすると同じキリスト教徒と言いましても、この宗派とこの宗派では意見が違うということになれば一緒にやっていくことができないということになります。迫害したり、あるいは殺し合いをしたりするという血なまぐさいところにつながっていくということもある。つまり、教会の中に国家があるという状態でありまして、国家の中に教会があるという構図ではないということであります。教会の中のパーツとして国家と呼ぶべきものがあると。そして、ローマ教皇はあらゆることについて、カノン法に基づく裁判例を持っている。人間のなすことやることすべて人間の魂のなせる業であると。人間の魂を管理するのが教皇の仕事でありますから、離婚はもちろんのこと、戦争ももちろんその魂のあり方にかかわるものとして批判されたり介入されたりする材料になるわけで、特に教会の財産に税金をかけようなどと考えると大きなトラブルが発生するということになりまして、やがてそのへんがこの信仰共同体の限界として出てくることになるわけです。(以下、略)
第16回 法学部同窓会総会・講演会(要旨)
「寄りかからず―清少納言と柱」
永井和子 学習院女子大学名誉教授
平成21年7月18日 百周年記念会館にて
本日は「寄りかかる」という身体的・精神的な姿勢について、平安時代の文学や現代の詩との関わりから資料をもとにお話したいと思います。
平安時代、中宮定子に仕えた清少納言の『枕草子』には「春はあけぼの・・・」で始まる約三百の章段があります。清少納言が精神的に「寄りかか」ったものを大まかに辿ると、まず自分自身、宮仕え後は中宮定子、定子没後はその思い出、そして自分自身に回帰、といったところでしょうか。身体的には「柱」に寄りかかった記述がありますので、この柱を主題として述べることに致します。
当時の寝殿造りの柱は直径30cm程で、柱と柱の間隔は建物毎に一定しておりその間を一間と申します。仏教伝来の影響とも言われるこうした立派な寝殿造りは、柱で囲った空間を屋根で覆い床を張った構造で、簾・帷子(かたびら)・几帳・帳・壁代・障子、屏風等の可動的で柔らかい遮蔽物により大空間を区切ります。従って坐る人間が寄りかかることができたのは、周辺に巡らされた不動の柱です。こうして柱は単に構造上の必然性だけではなく、生活空間の中で人間に密着して、非常に強い親近性の有る一つの場を成しておりました。
『枕草子』に登場する柱の機能に目を転じますと、「ものをつける」「そばに身を置く」「寄りかかる」と大きく三分できます。まず「つける」その「もの」は、薬玉や九月九日の菊等で、この機能は現在も変わらないでしょう。また「身を置く」のは、柱を目安として場所を示したり、恥ずかしがって蔭に隠れる、即ち、柱を遮蔽物として使ったりする場合で、これも今と変わりません。
三つ目の「寄りかかる」状態が本日の主題と重なるもので、数の限られた柱に寄りかかるのですから、結論的に言うと特権的な姿勢であったと考えられます。『枕草子』の内容を時系列で見ると宮仕えの初期には一条天皇や藤原道隆が寄りかかる記述があり、清少納言は柱に隠れておりました。少し後になると「廂の柱に寄りかかりて、女房と物語などしてゐたるに」(96段)のように作者の動作として記されるようになります。緊張の時期から、柱に寄りかかることができるほどに慣れた時期に至ったと言えましょう。しかし『枕草子』の柱はあくまで柱であり、必ずしも情緒的な意味を持たせているわけではありません。
『源氏物語』では、柱とそれに寄る人間との関係はかなり意識的です。柱に隠れる、或いは遮蔽物とする人は空蝉・紫上・玉鬘・中君等すべて女性。寄る人は尼君・源氏・明石君・真木柱・薫等で、身体の緊張を解いた静止状況に在って内面的な思考へと叙述が導かれる場面が多く見られます。またそれぞれが特定の「自分の柱」を持ち、身体の匂いが染み込んだ柱は人と一体化し、寄った人の記憶をよびさますことによって不在者の象徴ともなります。「須磨」の巻に、源氏が須磨に退去したあとで「(源氏が)寄りゐたまひし真木柱を(紫上は)見たまふにも胸のみふたがりて・・・」という一文があり、檜の立派な柱を真木柱と称しますが、紫の上は柱に寄って不在者源氏を偲んでおります。「真木柱」の巻には、髭黒大将が玉鬘と結婚したために、もとの北の方は姫君の真木柱を連れて実家の式部宮邸にお帰りになってしまった、という話が描かれます。姫君は紙に歌を書き、慣れ親しんだ柱のひび割れに差し込みます。「今はとて宿離(か)れぬとも馴れきつる真木の柱はわれを忘るな」という歌で、ここでは柱を自立した他者として呼びかけ、移動する人間と対比して固定した存在である柱を、情報伝達の具とする場面が見られます。
柱は人間の居住性にとっては不要かもしれませんけれど、人はこうして柱の多面性を活かし折り合いをつけ、拠り所とし、不安定な心身を支えて来ました。本来が高い天空を目指して森に息づく樹木でありこうした神聖な存在としての把握は現在も受け継がれております。同時に平安文学から見ると、それぞれの作品が寝殿造りに有る柱をそれぞれ固有に把握して描いていることが判ります。古今東西を通じて同様な傾向がありましょうが、こうして柱は内部空間を仕切る微妙な境界性を含みながら人間の生きる場を豊富に形成して来ました。
2006年に亡くなった茨木のり子さんに「倚りかからず」という詩があります(『倚りかからず』所収 筑摩書房 1999・10)。「もはや できあいの思想には倚りかかりたくない」で始まり、「倚りかかるとすれば それは 椅子の背もたれだけ」と締めくくられているこの詩は非常にすばらしいものです。「寄りかかる」という面のみで申しますと、人間は他に寄りかからなければ存在し得ないという認識と同時に、椅子が存在する近代社会を前提としております。正座が一般化するのは明治以降という考え方もありますが、現在の私達は平面に座位を長く保つのは大変難しくなりました。当時から最近まで日本人は平面に坐った状態で自立し、緊張を解く場合は柱に寄りかかる等の工夫をして心身のバランスをとっておりましたけれど、近代に至って椅子に寄りかかる姿勢が普通となりました。坐る文化から椅子文化への変化は精神構造の変化と無関係でしょうか。そして日本人はまだ椅子に坐る文化には馴れてはおらず過渡的状況にあると思います。「寄りかかる」と「柱」という言葉を巡って清少納言や紫式部が示すように、平面でも椅子でも、坐る姿勢に在って自分の心身を自在に保つ形を探し当てることは、生き物として基本的な、非常に大切なことと私は考えております。
[PROFILE]
女子学習院初等科、学習院女子中等科を経て昭和28年学習院女子高等科を卒業。昭和32年お茶の水女子大学卒業。昭和35年学習院大学大学院修士課程修了。平安時代を中心とする日本文学、老人と文学などが研究分野。
桜友会法学部同窓会は、9月26日(土)に理事会を開催し、新会長に後藤昭彦氏(昭和38年政経学部政治学科卒)を選出した。
任期は2年間。

渡辺 允氏(昭和24年初等科卒) 前侍従長
第15回桜友会法学部同窓会総会が、7月5日(土)、波多野院長、福井大学長、井上大学法学部長等をお迎えし、創立百周年記念会館で開催されました。当日は、梅雨明けを思わせる暑さの中、内藤桜友会会長はじめ卒業生110余名が参集。総会に続く講演会では、「両陛下にお仕えして」と題して、前侍従長の渡辺 允氏(昭和24年初等科卒)から、両陛下のご公務の様子や誰もが聞きたくなる「あれこれ」について、質疑応答を交えながら伺いました。懇親会は、会場を輔仁会館に移し、グラス片手に大いに盛り上がりました。

高島肇久氏
高島肇久氏(昭38政) 学習院大学法学部特別客員教授
今日は7月7日、来年の7月7日は北海道洞爺湖サミットの開会日です。サミットまであと1年。日本では5回目の開催になります。当初、外務省は京都迎賓館を使って開催したかったようですが、安倍総理の決断で洞爺湖になりました。そのかわり京都では外相会合が開かれます。
首脳会議は、7月7日から3日間行われます。でも、サミットはそれだけではありません。来年は次々に関連会議が入り、洞爺湖の首脳会議で締めくくりとなるのです。テーマは環境問題と開発問題。旱魃、豪雨、洪水といった異常気象、それに伴う食糧難と貧困。環境メカニズムが崩れ、貧しい人たちがとくにひどい目にあっています。これは地球の安全保障に関わる問題です。温暖化防止と開発途上国の貧困対策を急がねばなりません。
これらの問題を日本がどう取り上げていくか。日本のODA(政府開発援助)は減り続けています。世界から見れば、日本の熱意が問われるわけで、外務省はなんとか歯止めをかけたいと知恵を絞っています。 その先頭に立っているのが麻生外相です。日本のブランド・イメージを高めようとしています。ブランド・イメージとはソフト・パワーがどのくらいあるか、つまりその国がどのくらい魅力があり、他の国の人から尊敬を集める力があるかということです。軍事力や経済力といったハード・パワーの対極にある概念です。
麻生外相はマンガに着目しました。日本にはマンガという素晴らしいソフト・パワーがあると麻生氏は言います。ワシントン郊外のショッピングセンターに日本のマンガが並び、フランス語に翻訳された日本のマンガが出版されているように、日本のコミック、アニメ、ゲームは世界に浸透しつつある。日本のイメージを高めていくためにマンガを使うべきだ。当初は外務省の官僚たちも半信半疑でしたが、国際漫画賞の創設として実を結び、日本の文化外交に新しい風を吹き込むことになりました。
世界ではネイション・ブランドが問われるようになりました。それぞれの国のブランド・イメージです。そこに行って住んでみたい、働いてみたい国はどこか、といえば分かりやすいでしょうか。イラク戦争以来アメリカのイメージは著しく低下しています。日本のイメージは中国や韓国では低いのですが、欧米ではかなり高く、日本は信頼できる国かという問いに有識者の8割から9割が、信頼できる、どちらかというと信頼できると答えています。
問題はどうやってブランド・イメージを外交に役立てていくかです。皆さんの記憶にも新しい、国連の安全保障理事会の常任理事国入り、日本はさまざまな外交努力をしました。でも、うまくいかなかった。日本が常任理事国入りを言い出せば支援すると言っていた国が、現実にこの話しがテーブルに乗ると態度があやしくなってくる。日本に対する信頼はとても高いけれど、それが日本外交や国際的な地位の向上にはつながらないのです。
外交力はODAを倍に増やしてもダメです。問われるのは日本の発信力です。東京にいる外国のプレスが減って北京が増えている。北京のほうがニュースがある、魅力的だというわけです。中国に関する記事が増えれば、ますますメディアの関心が向いていく。大きな流れができつつあります。
日本の等身大の姿をどう伝えるか。論を立てて、英語で発信していく論者があまりにも少ない。北朝鮮の核実験やミサイルの連続発射があっても、インターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙のオピニオン欄に、日本人の書いた記事が出たことがありません。学者にしても論文のほとんどは日本語の印刷物として出されます。英語でインターネットに載せるということが極めて少ない。その結果、世界の有識者の目に触れる頃には時機を失したものになっています。
アメリカでは、政府が新しい方針や政策を出すとき、ファクト・シートという補足資料を豊富に出します。記者発表の後、間髪いれずに出てきます。背景説明があり、基礎的な数値が資料として示されますから、記者は深みのある記事が書けます。日本では記者が自分で調べなければなりません。締切に追われる記者にとっては無理な話です。日本の主張を世界にもっともっと伝えないと、国際社会の中で日本は存在感を失います。そのためには工夫が必要です。
英語によるテレビの国際放送をはじめたいと考えています。BBCやCNNは世界中で見られますが、これだけでいいのか。他の国は自分たちの考え方、ものの見方をテレビで伝えようとし始めています。日本でも放送法の改正が成立すれば、まもなく実現するでしょう。ただ、お客さんがつくかつかないかは、ひとえに内容にかかっています。日本人による日本風の放送ではお客さんはつきません。カタールのアルジャジーラは、アラブ系のメディアですが、英語放送にはユダヤ系のレポーターを採用し、他にもヘッド・ハンティングして優秀な人材を集めています。
今まで述べてきたような事柄を積み重ねることで、その国の存在感が高まっていくのです。いま、国際政治の中に真空状態ができてしまっています。そこにつけ入ろうとしている国がいます。自由、民主主義、人権、法の支配、市場経済という共通の価値観を持つ国が手を握り、提携していかなければなりません。
日本は世界での信頼感を高めると同時に自分たちの考え方やものの見方を発信する努力が必要です。洞爺湖には世界のプレスがやってきます。今日からまる1年、綿密な作戦を立て、日本の国際的な地位を確固たるものしていく努力が求められています。

戸松秀典氏
戸松秀典氏 学習院大学専門職大学院 法務研究科長
平成18年9月21日に、新司法試験合格者の発表がありました。マスコミも大きく報道しましたが、学習院大学は15名の合格者を出し順位は19位でした。朝日新聞は旧司法試験は25位であったとのカツコ書きを付けていました。
これを見た方々、特に学外からは、「学習院は頑張っている」と言われました。従来の試験では、わずかしか合格していませんでしたから、画期的なことだとの評価を得ました。
しかし、私は、法務研究科長として、3月に50名の修了者を出し、全員合格との信念で修了させましたので、不本意な結果ではあります。
我々法科大学院スタッフ全員、真剣にいろいろ分析して、今後の対応等を考えていますのでその結果を踏まえて法科大学院の現状と今後についてお話しいたします。
法科大学院の使命は、わが国は西欧と比べて法曹人口が少ないのでそれを増加させるとともに、戦後行って来た司法試験を通しての法曹育成過程にいろいろな病理現象が生じ、制度疲労まで起こしているのでそれを改革するということです。
司法試験予備校で学んで試験に合格した人が、2年間の司法研修所の修習を経て法曹になるのですが、十分な資質をもっているかどうかが疑われることが多くなってきました。
一回限りの試験による選抜ではなく、きちんとした教育をする法曹育成が法科大学院で、専門職大学院という位置づけです。
学習院大学は小規模で、財政能力上からも大きな大学院を作る訳にはいかず、いろいろ検討した結果、法学既習者50名の2年コースと、未修者15名の3年コースとに分けました。3年コースは、多様な資質を持つ優れた法曹養成が制度の趣旨のひとつですから、医師、歯科医師等の理科系の人にも法曹になってもらいたい、ということです。
入学生達は、朝から晩まで目の色を変えて勉強しており、学部の学生に良い影響を与えています。文科省の視察での学生への聞き取り調査で、「これほど教師に対する信頼感があり、大学への愛着感を持つ法科大学院はない」との評価もいただきました。
来年度からは、法科大学院の中に法務研究所を設け、いろいろな問題の受託研究を引き受け、その研究過程での成果を学生に還元することや、学習院に法律事務所を作ってそこで学生の実務教育をしたり関係者からの相談にも応ずるという様なことを考えています。
また、すでに法曹資格を得て活躍している人が、法科大学院に戻ってもういちど腕を磨き直すリカレントスクールも成り立つのではないでしょうか。それらによって、法科大学院は、必要不可欠、磐石なものになると考えています。
こいけひでお/昭和60年学習院大学経済学部経営学科卒業後NHKに入局。鳥取での5年の記者生活などを経て、政治部の首相官邸担当となる。マスコミ志望は名刺1枚でだれにでも会えるから。弁論部出身。この講演後、小泉内閣は解散。9月11日の総選挙の勝利で新たに小泉内閣が誕生。

小池英夫氏(昭60営)
小池 英夫氏(昭60営) NHK政治部記者
郵政民営化を改革の本丸と位置づけ、小泉内閣最大の課題として取り組んでいるが、国民に、今一番取り組んでもらいたい政策を問うと、郵政民営化は10位前後で、1位には福祉・景気・年金をあげている。小泉さんと国民の問に意識のギャップがある。
この内閣は小泉首相個人の人気によって支えられている。小泉さんと国民との関係は、若貴ブームと大相撲に少し似ている。90年代に毎日満員御礼が続くという空前の大相撲ブームがあったが、これは89年11月場所に貴花田が新十両になり、貴の花にしこ名を変えて、全盛期を歩み、97年5月に引退するまでの7年半のことだった。若貴ブームが去って、人気が下がると、両国の国技館だけでなく、地方に行っても、観客が半分位で、閑古鳥が鳴いている日もあった。あの空前の大相撲人気は若貴人気に支えられていた。
小泉首相は政治家の世界では変わり者で通っている。夜も寝るのが遅いようだが、朝が本当に弱い。火曜と金曜は閣議があり、国会開会中は午前8時から、閉会中は午前10時からだが、それ以外は11時以降に公邸を出ている。歴代の首相の中でも朝のスタートが遅い。
また、非常に多趣味である。歌舞伎、映画、オペラ、ミュージカル。今日から3連休だが、他の総理大臣だと3日のうち1、2日は政治家と会って、情報を仕入れたり、政策課題について議論したりする。小泉首相は自分の趣味に休日全部をあてている。
首相の1日の中で一番輝く時間がある。1日2回の記者団の質問に答える時間、午前11時半から12時と夕方6時から7時位の間で、特に後者はテレビが入るので目を輝かせ、ワンフレーズを話し、表情も豊かで、生き生きとしている。
「構造改革なくして景気回復なし」等のワンフレーズで、国民に分かりやすく、訴える。自分の言葉で言えるというのは小泉さんの力量・才能で、これまでの首相にはなかったことだ。
さらに、サプライズがある。国民をあっと驚かせて、支持率を上げる。ハンセン病の判決に関して、国は上訴するという見解が多かったが、夕方、官邸での会議後、記者団の前に現れた首相は、一言「告訴はしません。後は、担当大臣に開いてください」。普通第一報は担当閣僚、官房長官が言うのだが、首相の決断であるという印象を与える。
人事では、安倍幹事長や武部幹事長をもってきたり、衆議院の郵政民営化特別委員会の筆頭理事には自民党の副総裁を経験した、盟友の山崎さんをもってきた。野党との折衝で汗をかく仕事で、普通中堅以下の人をもってくるがサプライズの演出がうまい。
官邸サイドでサプライズを演出するということは、情報がどこかで漏れるとサプライズにならないということ。内閣の中で情報を知る人を少なくして、情報漏れを防ぐということで、ガードの堅い内閣だといえる。また、新しい総理大臣官邸ができたこともある。前の官邸はオープンで、記者は自由に行き来ができ、総理執務室の近くや官房長官の秘書官室まで行くことができた。今は1階に記者クラブがあり、3階に正面玄関があり、5階に総理と官房長官の部屋があり、常にアポイントをとらないと入ることができないので取材がしにくくなっている。
また、特徴的なのは変化を印象づけること。例えばクールビズを率先して行う。通信販売で買ったということですが、初日に沖縄の服を着て登場して、「これはいいだろう」と自分から投げかけ、変化を印象づける。国民は、変化に弱い。場面が変わると、興味をもつ。
もう一つの小泉政治の特徴は劇場型政治だと言える。強固な意思をもって政治を進めているというわけではない。反対派の納得を得られるよう郵政民営化法案の修正を行うのであるが、7月4日の国会答弁の中で野党の追及で修正しても法案は全く変わっていないと言い張り、強弁した。自民党内では評判が悪く、反対が増えた一つの要因になったが、自分の思いを劇場型で言い切ってしまう。
郵政民営化法案で衆議院で51人の造反が出た。参議院はギリギリで可決されるのではないか。参議院で否決されると、解散に打って出るだろう。
外交は、中国、北朝鮮、ロシアの北方領土、国連の安保理問題等八方ふさがりではないかと首相に質問したこともあった。3月までは予算で、4月から3カ月間郵政問題一本にしぼられていて、他の政策課題がストップしており、国益を損ねているという指摘もある。
小選挙区制は、党主の顔によって政権が選ばれていく、ある意味でリーダーシップを強くもった人の方が選挙に勝つ。小選挙区制度によって、政治の本質が変わってきていると言える。(講演要旨) 構成/田中進(昭48法)
こいけひでお/昭和60年学習院大学経済学部経営学科卒業後NHKに入局。鳥取での5年の記者生活などを経て、政治部の首相官邸担当となる。マスコミ志望は名刺1枚でだれにでも会えるから。弁論部出身。この講演後、小泉内閣は解散。9月11日の総選挙の勝利で新たに小泉内閣が誕生。











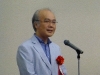















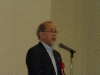




















































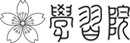 学校法人学習院
学校法人学習院 桜友会本部サイト
桜友会本部サイト