
平野 次郎氏
平野 次郎氏 NHK解説委員、学習院女子大学特別専任教授
アメリカの社会学者デイビッド・リースマンは、学者と知識人との違いを「学者というのは観念の中に生きる人間であり、知識人は観念を求めて生きる人間である」と言っています。
ジャーナリストというのは、自分の感情や嗜好に関わらず、事実を事実として受け止めるものです。対して学者というのは、事実の中から論理をつくりだします。そこに違いがあります。
コンバージアンスの原則というものがありますが、コンバージアンス(収斂)の原則とは、格差が存在する経済圏同士が、経済を交流させると、結果として格差が是正され、両方の経済圏にとってハッピーな結果がもたらされるという近代経済学の理論です。しかし、経済学者はその条件については配慮していない。その他の条件が一定であるという仮定に基づいて理論をつくる。しかしジャーナリストは一人ひとりの人間を見るわけです。そうすると、個に目が行き過ぎて全体を統一するひとつの理論をつくりあげることができないのです。これがアカデミックとジャーナリズムの違いです。
ジャーナリストは、自分が見たものを信じ、それをニュースにする。学者は、そういう一人ひとりの情報を集めて並べ、そこから統計的な理論をつくる。そうすると個の情報からは遠く離れてしまう。ジャーナリストと学者というのは、それぞれにこのような特徴があるのです。
東西ドイツが統一されて間もない頃、ポーランドの方が安いからという理由でドイツの主婦がポーランドでマルクで買物をしていました。
経済学では、100円の製品があるとすると、20円が原価で80円は労働賃金ということになります。では、ドイツとポーランドではどちらが労働賃金が高いかというと、ドイツのほうが5倍ぐらい高いんです。そうすると、ドイツで100円のものをポーランドで買うと20円で買えるわけです。私は、これが冷戦が崩壊したということの現場での事実なんだとそのときわかったのです。現場の人たちにとって、冷戦が終わる前と終わったあとで何が違うかというと、昨日まで買いに行けなかったところへ買い物に行ける、安いものが買えるようになったということなんです。ジャーナリストはそういうものをいつも追いかけています。個人の生活の話を通して全体を理解させようとしているのです。学者は個人の生活よりも全体を、そして個人を見てもなるべく平等に扱おうとします。それはどちらも正しくてどちらも少し正しくないと思います。
この話の中からドイツの主婦たちが毎日ポーランドへ安いじゃがいもを買いに行って、ポーランドの労働者がドイツに働きに行くということが続いている間に、両国の物価、労働賃金、経済の水準が等しくなるというのがコンバージアンスの法則です。問題は、この法則は確かに働いているけれども、物理のようにはっきりとは目に見えず、ときとしてその法則に逆行するような現象もあるということです。そこが学者には説明がつかない、絶対に教えない分野です。そういう人的な要因というのはさまざまなところに顔を出す。だからニュースというものが発生し、それを追いかけるジャーナリズムというものが存在するのだと思います。
ジャーナリストは、このような現象を一つひとつ拾ってきては面白おかしく伝えているわけですが、学者は早くて5年、遅くて10年たたなければ論として確立することはできないだろうと思います。
これは、すべてのイマジネーションの源なんです。
私は学生にいつもこう言っています。「Don’t panick」。何が起こってもパニックを起こすな。そのためには、世界のことをよく知って日本を理解しなさい。そして日本のことをよく勉強して世界に説明できるような力をつけなさいと言っています。それは多分にジャーナリスティックなことでありアカデミックなことであろうと私は思っています。

森山英一氏(昭34政)
森山 英一氏(昭34政) 元福島地検検事正、現中野公証役場公証人
[法律家として] 子どもの頃から歴史が大好きで、歴史家になろうと思っていた。検事だった父が早く亡くなり、一人っ子で皆が法律家になることを期待した。大学に進学して、司法試験の受験を決意したのが高等科3年の時である。
昭和30年に小田成光氏が大学在学中に初めて試験に合格した。その後、毎年のように合格者が出た。試験のために結成された法学研究会に入部し、勉強したが、受験者が少数で効果が上がらない。当時大学の先生方もあまり熱心ではなかった。困ったのは卒業してから仲間と勉強する場がなかったことである。部外者に開放されている中央大学の答案練習会に参加し、明治大学の研究会の聴講生にもなる。多数の研究会があり、合格者数を競っていた。大学の支援体制や設備が整っていることに驚嘆した。試験には3回目に合格した。
試験が難しくなり、合格者が高年齢化し、試験の改革が進められている。当時は合格後2年間の司法研修所教育で知識が平均化され、法曹としての一体感が養われたが、新制度では1年間もなく、研修所の良さが失われてしまう。アメリカのロースクールのようにどの法科大学院を出たかによって評価が定まってしまうのではないか。
検事は独任制の官庁(一人で国を代表する)であり、公益の代表者である。オーム真理教の解散請求は検察官が行った。
33年間検察官を勤め、現在は公証人をしている。公証人は11世紀のイタリアに起源し、文学作品に多く登場している。仕事は公正証書作成であるが、最近は遺言・離婚等予防司法的なものが多くなっている。
[城の話] 昭和19年戦局が急速に悪化し、学童疎開も始まった。幸い父の転勤で仙台に行くことになった。その頃の仙台は、城下町の面影がよく残っていた。官舎の前の広瀬川を隔てて仙台城の大手門が見えた。当時の仙台は軍都で、仙台城には第二師団の司令部が置かれていた。大手門は伊達政宗が豊臣秀吉から肥前名護屋城の大手門を拝領したといわれ仙台の象徴である。昭和20年7月の戦災で消失し、現在まで復元できていない。
父の弘前出張で弘前城の絵葉書をもらい、ひどく感激する。城がすっかり好きになった。父に頼んで各地の城の絵葉書を集めてもらった。城の絵を描き、城に関する本を集め、歴史書を読むなど、だんだん病膏盲に入る。昭和21年7月に帰京した。
輔仁会の部で高等科に史学部があったが、中等科の生徒も参加できるというので入部した。活動内容は考古学で意外に思った。先輩には岡田茂弘、徳川義宣、永田良昭現大学長ら諸先輩がおられた。発掘調査などの合宿もあり体育会系と同じ生活で、今でも親しく付き合っている。
大学入学後、司法試験に合格するまでは城の研究は休眠した。司法修習生になって、日本城郭協会に入会した。江戸城や外国の城にも関心をもった。明治維新の城が現在どうなっているのか誰も調べていない。まず、城の法制から調べてみたらどうだろうかと考えた。昭和45年に「名城と維新-維新とその後の城郭史」を自費出版した。平成元年に50歳になった記念に明治維新のときに存在した約340の城と陣屋の維新後の変遷と現状をまとめて「明治維新廃城一覧」として新人物往来社から刊行した。現職の検事が城の本を書いたというので、各新聞で取り上げられた。仕事が忙しい時は3、4年も城の研究を中断した。転勤を利用して地の城や陣屋を巡った。また、検事の捜査権と個人の調査の落差に驚いた。検事が捜査で手に入らないものはないが、個人で研究するとそうはいかない。
人間は暇だと何もしない。自分を制約するものが刺激剤になる。自分をむち打つようなものがないとなかなか事はできない。
研究の成果としては、関連した事項に関心が広がっていくことである。城に関連して軍事、芸術、宗教など色々な分野に興味を持った。城は歴史がわからないと理解できない。西洋史をかなり学んでようやくヨーロッパの城をいくらか理解できた。 (講演要旨)
大三輪 龍彦氏 (昭和40史)鶴見大学文学部教授
鎌倉の歴史と伝説を尋ねて「秘宝拝観寺社めぐり」の地図を資料に大三輪様の発掘成果を中心に「古都鎌倉の中世都市空間」という掲題でお話を伺いました。
軍事都市から政治都市へ
鎌倉が大きく変わったのは実朝が暗殺されて、その後1224年に後鳥羽上皇が幕府を倒そうと兵を挙げ、承久の乱が起き、幕府側の勝利に終りますが、そこでそれまで公家と武家の二元政権であったのが、一元政権に変わります。武家政権の中心である鎌倉はこの時点から武家政権の軍事都市から政治都市としての顔を持つように変わらざるを得なくなります。ここで要害の地としての軍事都市と多くの人々を受け入れる政治都市とのジレンマが起きます。
北条泰時の時代(1224年~1242年)に大規模な土木工事が行われ人工的な街づくりがなされました。まずなされたのが通り易い道を作るために尾根を切断することでした。ただしそこから簡単に敵が入れないようせいぜい馬一頭が通れる幅にしました。尾根を断ち割ったものを切り通しといいます。鎌倉では七ヶ所の切り通しが作られました。
次になされたのが山の斜面、鎌倉の内側を垂直に切り落として、その時に出た土砂を前に埋めたてることでした。その結果、敵が山に登った時は垂直の崖から降りられなくなります。これにより谷ばかりで平地の少をかった鎌倉を埋め立てて平地を増加させました。
このように軍事的要素を残したままで政治都市への転換が図られ鎌倉の空間利用の変化が起きました。
道路と空間利用
まず若宮大路を中心軸とし西側には和田塚といったあたりを通っている道、これを今小路といいます、それと八幡宮の鳥居から右の方へ行きますと法戒寺というお寺がありますが、法戒寺から滑川(なめりがわ)を渡ってくる道を小町小路といいます。八幡宮の前を横に通っている道を元小路、二つの川が合流している所を町小路、これら四本の道路で囲まれた内側が鎌倉の中枢部となります。
その周りに武家屋敷等が作られます。小きな谷と山の頂上に周縁部という空間があります。この空間はそれぞれの意味を持ちます。四本の道に囲まれた中に妙本地・本覚寺等の四つの寺がありますが、これらは室町以降に建てられたものです。するとこの四本の道に囲まれた地域には当初はお寺はなかったということになります。京都でもそうですが、郡市の中心である聖をる空間に死のけがれを持ってくることは嫌います。京都に寺町通りと同様、そこのお寺もすべて後から引っ越してきたお寺です。
鎌倉では鶴岡八幡宮から若宮大路という聖なる通が南の舞浜という海岸へ向って南北に走っています。若宮大路は最近の発掘調査で側溝がたくさん出てきています。これらは木組みで幅が3m、深さが1.5m位あります。
東側と西側で調査をしましたが、この間が当時の若宮大路の幅になります。これは33mです。側溝を入れると37mです。側溝はそれぞれの武士たちに命じて作らせたらしく側溝の下から木簡が出てきます。それは一条=3mの寸法でこれに請負った武士の名が書かれています。
それからもう一つ分かってきたことは、若宮大路のわきに武家屋敷があるのですが、武家屋敷の正面は若宮大路に直接面してなく、勝手に大路には出入りをさせないようになっています。反対側に出入口が作られていました。これはたぶん若宮大路が最終防衛線としての軍事的意味を持っていたのだと思います。幕府の重要な機関は若宮大路の東側に持っていった。西から敵が進入してくることを仮想していたのでしょう。
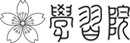 学校法人学習院
学校法人学習院 桜友会本部サイト
桜友会本部サイト