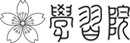from Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E5%B8%82
長崎市(ながさきし)は、九州の北西部に位置する都市で、長崎県の県庁所在地である。国から中核市に指定されている。中国風に崎陽(きよう)と呼ばれることもある。
古くから、外国への玄関口として発展してきた港湾都市である。江戸時代は国内唯一の貿易港出島を持ち、ヨーロッパから多くの文化が入ってきた。外国からの文化流入の影響や、坂の多い街並みなどから、日本国内の他都市とは違った景観を保持している。また、長崎県下最大の人口を持つ長崎の中心都市である。
市域面積の13.1%である市街地に人口の約78%が住み、市街地の人口密度は、7900人/km²と過密である。
年表

大正の市役所本館、手彩色絵葉書
- 1567年 – 宣教師ルイス・デ・アルメイダによるキリスト教の布教。
- 1570年 – 大村純忠、わずか百戸あまりの寒村であった大村領長崎を開港(いわゆる長崎開港)。
- 1571年 – ポルトガル船来航(~1639年)。
- 1580年 – 領主大村純忠、長崎・茂木をイエズス会に寄進。
- 1582年 – 天正遣欧少年使節出発。
- 1592年 – 豊臣秀吉、長崎を直轄領とし奉行を置く。
- 1597年 – 豊臣秀吉による日本二十六聖人の処刑。
- 1604年 – 糸割符制度。
- 1605年 – 江戸幕府、長崎を天領とする。
- 1622年 – 元和の大殉教でキリシタンたちが殺害される。
- 1635年 – 出島完成、ポルトガル人を収容する。
- 1641年 – オランダ東インド会社の平戸商館、出島に移転。
- 1673年 – 英リターン号来航、通商要求は拒絶。
- 1689年 – 唐人屋敷完成。
- 1690年 – エンゲルベルト・ケンペル来日。
- 1698年 – 長崎会所設置。
- 1804年 – ニコライ・レザノフ来航。
- 1808年 – フェートン号事件。
- 1823年 – シーボルト来日(翌年、鳴滝塾開設)。
- 1828年 – シーボルト事件。
- 1853年 – プチャーチン来航。
- 1854年 – 長崎港を開放。
- 1855年 – 長崎海軍伝習所開設(~1858年)。
- 1859年 – 出島オランダ商館閉鎖。
- 1865年(慶応元年) – 大浦天主堂のベルナール・プティジャン神父、隠れキリシタン発見(いわゆる信徒発見)。
- 1867年(慶応3年)- 浦上地区で発見されたキリスト教徒への弾圧事件(浦上四番崩れ)。
- 1870年(明治3年)- 外国人居留地完成。
- 1878年(明治11年)- 長崎区役所設置。
- 1886年(明治19年) – 長崎事件。寄港中の清国(中国)水兵による暴動。
- 1889年(明治22年)4月1日 – 市制施行で長崎市が発足する。
- 1899年(明治32年) – 居留地回収。
- 1923年(大正12年)2月11日 – 長崎-上海間に日本郵船による日華連絡船航路の運航が開始される。
- 1940年(昭和15年) – 三菱重工長崎造船所で戦艦武蔵進水。
- 1945年(昭和20年)8月9日 – 午前11時2分、アメリカ軍により原子爆弾が投下される。7万人以上の住民が死亡し、市内家屋の約36%が壊滅。
- 第二次大戦後
- 1955年(昭和30年)8月 – 平和祈念像完成。
- 1972年(昭和47年)10月2日 – 長崎トンネル(長崎本線・新線)開通。
- 1977年(昭和52年)
- 10月15日 – 平戸発長崎行きの西肥バスが阿蘇赤軍を名乗る人物によりバスジャックされる(長崎バスジャック事件)。
- 11月 – 国際観光文化都市に指定される。
- 1981年(昭和56年)2月 – ヨハネ・パウロ2世長崎訪問。
- 1982年(昭和57年)7月23日 – 最大1時間雨量が111.5mmという記録的な大雨が降り299人が犠牲となった(長崎大水害)。
- 1990年(平成2年)1月18日 – 本島等市長銃撃事件発生。
- 1991年(平成3年)- 東山手・南山手が、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定される。
- 1997年(平成9年)4月1日 – 中核市に指定される。
- 2007年(平成19年)4月17日 – 伊藤一長市長射殺事件発生、市長は翌日午前2時28分に死亡が確認された。
※行政区域の変遷は別記。
事始め
- 英字新聞(日本初、ナガサキ・シッピング・リスト・アンド・アドバタイザーを参照)
- 国際電信(日本初)
- 缶詰製造(日本初)
- 汽車(日本初の蒸気機関車が走った場所である。慶応元年(1865年)イギリス人商人のグラバーが上海から輸入した英国製蒸気機関車「アイアン・デューク」号を大浦海岸(数百メートル)で走らせたことから、長崎市梅香崎町の市民病院前に「我が国鉄道発祥の地」の碑がある。「鉄道発祥記念碑」は日本で初めて鉄道の営業運転(1872年)が行われた横浜市にある。日本の鉄道史を参照。)
- 気球飛揚の地(日本初)
- コーヒー(伝来)
- ジャガイモ(伝来)
- 鉄橋(日本初)(銕橋を参照)
- バドミントン(伝来)
- ボウリング場(日本初)
- ヨット(日本初、英国人船大工が英国商人の注文で建造)
天領 長崎
- イエズス会領から天領へ
- 大村純忠の領地であった長崎村は、1580年にはイエズス会領となり、1588年には豊臣秀吉の九州征伐により、秀吉の直轄領となった。その時、代官に任命されたのは、佐賀の鍋島直茂であり、4年後の1592年には後任として肥前国唐津(佐賀県唐津市)の寺沢広高が長崎奉行となった。寺沢は関ヶ原の戦いにおいて東軍についたため、江戸時代に入ってからも引き続き長崎奉行を務めた。
- 市中と郷
- 長崎奉行の管理下にあった天領としての長崎は、「市中」という内町・外町と、「郷」という農村部から成っていた。内町は、大村純忠が1571年に 造った6町(島原町、大村町、外浦町、平戸町、横瀬浦町、文知町)をはじめとして、1593年までに本博多町、本興善町など23町が成立していた。外町 は、材木町、本紺屋町、袋町、酒屋町などで、1597年に内町との町域を定めた。
- ポルトガル等との貿易によって栄えた長崎は、町の区域が徐々に拡大していったが、その領地は幕府領と大村領に混在していたため、1605年に幕府領の一部と大村領の一部を交換し、円滑な支配が行えるようにした。
- これにより「市中」と「郷」からなる天領長崎が確立したが、外町の町域はその後も拡大を続け、1672年には内町26町、外町51町とされ、両町合計77町になった。さらに、外町の出島町と遊郭のあった丸山町、寄合町の3町を加え、80町となった。1676年には外町の検地が行われ、これによって長崎の町域が決定した。1699年には、内町と外町の区分が解消されている。
長崎海防掛として大村藩の九州長崎氏血族の中村喜八郎を組頭に近隣諸藩より長崎永代勤番耳役として長崎十人組を組織し幕末の1857年、外国人居留地を建設するために大村領戸町村が幕府に没収されたが、この時までは上記の体制が続いた。
※行政区域の変遷は別記。